ポケモンはLGBTQコミュニティーの象徴!?国境を超えると大変化するブランドイメージ事例と海外マーケティング提案
ウォード 涼子

ポケットモンスター、通称ポケモンは、発売当時から世界中で愛され続けていますが、イギリスも例外ではありません。「ポケモン、ゲットだぜ!」は、英語では’Gotta catch ‘em all!’とローカライズされ、このフレーズを耳にすれば大人も子供も、「ポケモンのことだ」とすぐに分かるほどマーケットに浸透しています。
イギリスで愛され続けるポケモン
一番最近発売されたばかりの『ポケットモンスター ソード・シールド』は、イギリスで爆発的な人気を誇り、ソードは2019年で売上No.1、シールドはNo.3であったとされています。2010年に発売された『ポケットモンスター ブラック・ホワイト』に比べ、イギリス国内で33%も売上個数を上げたとも記録しています。また、同ゲーム発売に伴い、プレーに必要なニンテンドースイッチの売上がイギリス国内で30%増加しました。
このように、発売から数十年経つ今もイギリスで人気の衰えないポケモンですが、実はイギリスを含む欧米マーケットで「意外な」捉われ方をしていることはご存知でしょうか。今回は、国境を超えるだけでそのイメージが変わる可能性のある日本ブランドの例として、その具体的部分をご紹介します。
ポケモン:日本でお馴染みのゲームが、欧米で意外な(?)捉われ方をしている件
クィアカルチャーとの深い関係
欧米マーケットにおける、ポケモンの「意外な」捉われ方とは、何でしょうか。一言で言えば、それは「’クィア’との関係」と言えます。
「クィア」とは、Out Japan Co., Ltd.によれば、「クィアという言葉を用いたときのニュアンス、本来の意味合いは、一言で説明するのが難しい、やや複雑なもの」であるとしつつも、LGBTQやLGBTQ+の「Q」であったり、「セクシュアルマイノリティの総称」と説明されています。(詳しい背景やニュアンスをお知りになりたい方は、出典元であるこちらをご参考下さい)
実際、英語で「ポケモン クィアカルチャー」などと検索してみると、かなりの量の関連記事が検索結果に現れ、その強い関係性が伺えます。
インクルーシブな「コミュニティ」とポケモン
それでは、なぜそんなにも欧米ではポケモンとクィアカルチャーの関係性が強いのでしょうか。
Pride Mediaは、「クィア」な人たちがこれまでもポケモンを愛する理由の一つとして、「コミュニティを強調している点」を挙げています。
「友達と一緒にプレーや、想い出の共有を促すことで、ポケモンはコミュニティを非常に強調している・・・(中略)・・・自分のように変な、仲間外れにされていると感じているような子どもが、ポケモンを通じて似たような人や繋がりを見つけていけた。その仲間外れにされていた人達が、今のクィアの若者世代なんだ」(Pride Mediaの記事の一部を筆者が和訳)
と説明されています。
また、Gay Star Newsのある記事では、ゲイであるポケモンファンにその理由についてインタビューしており、取材された、イングランド出身の30歳(22年間以上のポケモンファン!)はポケモンを通じて見つけた友達に救われたと答えています。
「ほとんどの生徒が白人で異性愛者という環境のノーフォークの田舎の学校で、混血、さらにゲイである自分にとって、溶け込むのはとても難しかった・・・(中略)・・・(ポケモンをを通じて知り合った友達は)カミングアウトするサポートもしてくれたし、今でも友達です。」(Gay Star Newsの記事の一部を筆者が和訳)
子どもの頃、他の人と何か自分が違うと感じていても、ポケモンを通じて仲間を見つけられたという記憶、そこからくる安心感やノスタルジーなどから、「クィア」な大人になった今も、大のポケモンファンであり続けているということが伺えます。
性別を超えた存在としてのポケモン:「ノンバイナリー」、「ジェンダーレス」
ポケモンがクィアカルチャーと関連付けられる理由として、キャラクターの描き方が「ノンバイナリー」である点がよく挙げられています。「ノンバイナリー」とは、一言で言えば、男性と女性という二極分化を超えた性の在り方、と言えます。
具体的には、ポケモンに関する何がノンバイナリーとされているのでしょうか。
アニメ版ポケットモンスターに出てくるロケット団員であるムサシとコジロウが、その代表として捉えられています。ムサシとコジロウや、二人が持つ「悪役」ポケモンたちが、女装、男装するなど、社会的ジェンダー規範を超えた形で描かれている点に、「クィアさ」を見出していると言います。また、キャラクターの女装がドラァグカルチャー(詳しくは、こちらをご参照下さい)を連想させる事も挙げられると言われています。
また、初代ポケモン151匹のうち、106匹がオス・メスに分かれていましたが、それ以外のいくつかのポケモンはジェンダーレスであった点も、LGBTQコミュニティから共感を得ています。

出典: https://pokemongo-raku.com
ある記事では、明らかにノンバイナリーとわかるようなキャラクターだけでなく、「151匹のポケモン全てがクィアであるその理由」と題し、どれだけポケモン全体がLGBTQコミュニティと関わりが深いかといった内容を説明しているものもあります。
このような理由から、ウィキペディアの英語ページでは、「LGBTキャラクターの出てくるゲーム」の一つとしてポケモンが挙げられているほどです。
クィアアーティストの表現素材としてのポケモン

このようなポケモンとクィアカルチャーの結びつきは、更なる表現へのインスピレーションとしても働いています。
例えば、PinkNewsの記事では、ポケモンをル・ポール(RuPaul/アメリカ出身の、ドラァグクイーンのカリスマ)のドラァグクイーン・レースに見立てたコンテンツを発表し、ネット上で話題になっているとのニュースを伝えています。
ル・ポールのドラァグクイーン・レースとは、全国から集まったドラァグクイーンたちが、パフォーマンスで競い合い真のクイーンを決めるというもの。元々アメリカで人気を博したTV番組ですが、最近イギリスを舞台にした番組も放映されるようになり、イギリス国内で特に話題になっていました。
まとめ
今回のブログでは、おなじみのポケモンが、欧米では実はLGBTQのアイコンとして良く知られている事例について紹介しました。同じ製品やサービスでも、国境を超えるだけで捉われ方が変わり、それに応じてターゲット層なども検討し直す必要性が示唆されます。
東京エスクでは、お客様の製品やサービスの、欧州マーケットでのテスティング、消費者動向調査などを通じ、海外進出をサポートしております。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせ下さい!




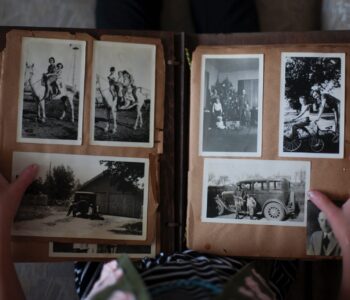



![[2022年版]イギリスでこれから伸びる3つの業界 UK](https://tokyoesque.com/wp-content/uploads/2022/01/charles-postiaux-Q6UehpkBSnQ-unsplash-scaled.jpg)
![[ビジネスコラム]イギリス市場進出に成功した日本企業事例と成功の分析 イギリス市場進出に成功した日本企業事例](https://tokyoesque.com/wp-content/uploads/2021/12/hao-wen-NZ6QsjRhFeE-unsplash-scaled.jpg)
