 インタビュー
インタビュー
CBD弁護士新城安太先生が語る日本のCBD市場:市場拡大のエンジンとなる鍵とは?第2部
作者: 増野謙、アレクサンダー・ブラウン

CBD弁護士の新城安太先生との2部構成のインタビューシリーズの第1部では、新城先生が日本のCBD市場の全体像を描き、現状日本のCBDに関する規制と、規制緩和が日本市場への進出を目指している海外企業にどのような影響をもたらすかを説明します。
この第2部では、新城先生がマーケティング、CBD自体に対する認知度向上、公的機関による承認、CBD製品の検査プロセスなど、国内外の企業が日本市場で成功を収めるのを妨げている障壁について、さらに詳しく解説しす。
海外進出をお考えですか?お問い合わせはこちらから
増野謙:難易度の高い工程を経て日本に参入している海外企業も多々あると思うのですけども、現状先生がお考えになる海外からすでに進出しているCBD企業のこれらの成功や成長妨げている障壁である要因は何とお考えでしょうか?
新城安太先生:そうですね。まず、現状日本ではおそらくCBD市場で成功している海外企業というのは存在しないという事になります。海外企業どころか、国内企業でも、経済的な意味で成功している企業はゼロと私は認識しています。その理由としましては、特に海外企業に言ってしまうとやはり、まず一つ日本特有な問題として挙げられるのが、広告規制の話ですね。もちろん海外にも程度の差はありますし、広告規制もちろんありますが、日本ではCBDの効能効果というのは一番訴求したいポイントですね。
そこにつきまして、本来WHOでいろいろ報告書、「こういった症状に効いた論文がある」みたいな話を、本当はマーケティング上したいのですけど、それが日本の広告規制の問題で、一切言えないというものになります。なので、結構本来は上質なCBDをやっていて、きっちりしたエビデンスをちゃんとお持ちの海外企業は、かなりありますけど、そのエビデンスを使えないという状態にはなっていますので、マーケティングの面でどうしてもそこはその海外企業の本国でのマーケティングとはまた違った対応が求められます。
あとは、やはり日本人は基本的に、大麻について「ダメ」、「扱っては絶対いけません」というような教育をされて育ってきておりますので、大麻そのものに対する疑問、怖さみたいなことは実はマス層では感じているのが現状です。
そのような状況の中で、エビデンスに基づいたマーケティングができない、かつ、日本での歴史が浅い海外企業が、よくわからないCBDのことについて売っているのは、どうしても怪しく見えてしまいますね。もちろん、各社さんがかなり努力をされていて、パンフレットなど綺麗なものをご作成いただいたり、言えない効能効果をイメージさせるようなものを多少作ったり、あとは有名な海外のモデル、セレブの方、日本の芸能人もインフルエンサーなどの方も起用して、ブランドイメージを高める取り組みをされている企業さんはいくつか知ってはいま。それでも、マーケティングがやはりどうしてもうまくいっていないです。
私の肌感として、どうしても「怪しい企業の大麻由来の商品だから何となく怖い」というのが払拭していないというのが海外企業が成功できていない理由なのではないかと思っております。
増野:ありがとうございます。確かにそうですね。せっかくあるエビデンスを使えないというのは確かに八方塞がりという表現しかないと思います。
新城先生:はい。
増野:商品を売ろうとする時に伝えられないというのは歯がゆいと、おそらく各企業が感じていると思います。弊社にも繰り返しになりますけど、問い合わせが来ている中で、その現状を踏まえたうえで、「どうするべきか」を常に考えております。
例えば英国ではCBD商品はかなり出回っていますけども、やはり漢方に似ているところがあるのかなと考えております。
ある程度のエビデンスがありますけど、製薬会社さんが作っているような薬品とは少し違います。その中で、例えば日本の漢方業界を見た場合、PMDAの承認などが今後の市場拡大に対して、有意義なものになりますか?また、そのPMDA承認を得るまでの障壁等について、お考えを聞かせていただけますでしょうか?
新城先生:はい。日本では漢方は基本的医薬品として分類されますので、そのPMDA承認をもしされて、日本で正式に医薬品として販売、刷りできるのが実現した場合にはかなりポジティブなことになります。マーケティング上もかなりやりやすくなってきます。日本で医薬品承認されると、承認された効果、効能はもちろん広告で訴えることができますので、広告規制に関係なくきちんとマーケティングもできるようになると思います。
あとは医薬品としてちゃんとPMDAが承認していることは安全性など、そういったものに関して基本的には承認を得ているということになるので、かなり強い権威性にもなりまして、安全性も加えるとマーケティング的にはすごい重要なことになると思います。
ただ、やはり現実はなかなか上手くいかないのが現実でして、PMDA承認で医薬品の手前に、医薬部外品という医薬品と化粧品の間の中間的な分類が日本ではございます。医薬品よりは症状が緩和なものなのですけど、化粧品と違って有効成分がちゃんと入っているような物ですね。育毛剤、シミを改善できる化粧水、美容液など、そういったものが医薬部外品としてはカウントされますけど、「それにCBDを入れましょう」みたいな動きは現在あります。
実際にそれを実現しようと動いている企業さんはありますが、なかなか難しいのが、CBDの成分としてしっかり分析できる体制が日本でなかなか揃っていないというのがございます。CBDは単体としてどういった効果があるのかを、日本でちゃんとしたエビデンスを持っている実績もないので、まずエビデンス作り、論文作りから始まるということでかなりの費用がかかってしまうので、それに見合う効果効果があるのかどうかは正直まだよくわからいというのが現状です。
よって、大手の製薬さんは基本的には現状、潤ってる企業さんが多いので、あえてそこに参入する必要はないと考えている方もいらっしゃいます。そうするとやはり、あまり資本力がない中小企業の方がそれを目指すことになるのですけど、なかなか資金調達が上手くいかず、その費用を工面が出来ないというところが障壁にもなっております。

あとは、これはもしかしたらCBDの特有の問題なのかもしれませんけど、CBDも含めてカンナビノイドというものが、大麻由来の成分になるのですけど、体の方にどのように作用しているのか、いわゆるその作用・効果・効能を絞ることが、いろいろなとこにどうしても作用してしまうので、意外とこれが難しいらしいです。
これは私も早稲田大学の薬学系の教授の方に聞いた話なので、伝聞ではあるのですけど、実際に「CBDはどういった効果効能があるのか」というのをちゃんとエビデンスを作るために治験をしようと思っても、作用するようなところが、対象が多いのでなかなか思ったような仮説通りに行かずに、それがエビデンスを作る妨げにもなっているのという少し特殊な事情があるようです。
なので、そういった面でも少し医薬品承認としてPMDA承認がなされるまでには、CBD自体の問題とCBDを扱える検査機関など、CBDに詳しい人があまり日本にいないということと思います。あとは、そこにかけるコストをかけられる企業さんがいないという結構この3つぐらいの問題で、PMDA承認というのが、今の現時点ではあまり現実的ではないのかなと思われるとこではございます。
ただ、これに関しては法改正が進んで、CBDがより一般的なものになってきたら、可能性としてはあると思っております。個人的にはそれを期待しているところではございます(笑)。
増野:承知しました。やはり法改正がいわゆるビッグバンのような存在になり、そこから資本が集まりだす道筋が一番現実的なのですね。ありがとうございます。
それと、日本ではCBD商品に対するオンライン広告の規制があると伺っています。これはCBD商品自体も、企業側からも、日本での認知度を上げる機会が失われているという理解です。それで、すでに伺った効能効果が言えないというの以外にも、オンラインのプラットフォームに限った規制は何か理由がありますでしょうか?
新城先生:はい。今おっしゃっていただいた話でいうと、例えば、Google、Meta、あとはTiktokなどのそういったSNS、検索エンジンなど、より多くの方がネットをしていて見るようなブラウザー、媒体、というのはほとんどがCBDに関する広告を禁止しております。
理由としては、本当にシンプルな話でして、大麻由来の成分だからということになっております。なので、意外としかも、Google、Metaなどの国際的なプラットフォーム企業はグローバルで大麻がまだ非合法な国の方が多いので、グローバルで大麻由来の製品を禁止している。
だから、日本でも、そのルールが適応されて、広告が禁止されている。Tiktokも同じですね。そういった形で、規制がされております。なので、理由としてはもうシンプルに、大麻というのがもともと各国で非合法な国の方が多くて、「非合法なものを広告するのはプラットホームでは許しません」という理由で、それが禁止されているところではございます。
ただまあ、最近少し時流も変わってきておりまして、Googleが今年の1月が2月ごろにカリフォルニア州という大麻が合法な州に限定して、CBDに関する広告を規制緩和をして、テスト的に試験緩和をしていくような流れもあります。広告ではないのですけど、Amazonの方で、去年の4月から日本でもCBD商品取り扱いが可能になりました。なので、徐々にCBDに関しては寛容なグローバルな流れもありまして、Googleなどの広告出稿の流れもおそらく日本にも来るでしょうということは予想されております。
増野:そうですね。やはり、徐々にですけど、グローバルでも流れは変わってきている感じは出ていますね。
新城先生:おっしゃる通りですね。
増野:日本市場をアジア市場への入り口として見ているCBD企業が非常に多いと思います。「規制緩和がまず最初にあって、そこから色々ができる」という話を伺ったのですけども、それ以外にも何か日本のCBD市場がこれから成長していくことに必要なものがあればお聞かせください。
新城先生:はい。そうですね、これは私も常にクライアントさんと知恵を絞りながら考えているところではありますけど、まず一点は、CBD自体に対する一般的な認知度がやはりほとんどない。私はこの業界にいますので、どうしても道行く人すべてがCBDを知っていると錯覚してしまうのですけど、実際はそんなことはなくて、日本人でも10人に聞いたら1人知ってるか知らないかぐらいの確立でしかCBDが認知されておりません。なので、CBDに対する認知の拡大が、まずは日本で市場が伸びる一つの要因になるかと思っております。
その認知が拡大するためにどうすればいいかというと、先ほどの、規制緩和に若干かぶってしまうかもしれませんけど、例えばデジタル広告が解禁になって、一般の方々がよく目にするような成分であれば、基本的にそれはあまり知るような認知に関してはそれでできるようになります。続きまして、大企業がそこに参入してくるとマーケティングコストをかけて認知活動を広めてくれるので、そういったこともかなり重要になるかと思います。
あとは、CBD自体に対する認知度とも若干かぶってくるのですけど、CBD自体に対する怪しさか、大麻由来の成分ではあるのですけど、思ってるような大麻とはまた違う、というCBDに対する理解がもう少し広まれば、かなり選択肢としては増えるのかなと思っております。
あとは最後に、価格の話ですね。私が最初CBDにかかわり始めた時よりCBDの原料はおそらく4分の1ぐらいから、3分の1とかそのぐらいには価格が落ちてきているイメージではあります。ただどうしても輸入コストなども含めて、日本に輸入に対して特別なケアをしないといけないことから価格というのはやはりまだ高いままではありますと。で、そうなってくるとなかなかCBDの、最終的な製品の価格というのは下げづらいことがございまして、どういったブランディングで売ってるかみたいな話もあります。
例えば今、CBDのグミ五粒入りで、日本円で2500円、3000円など、少しまたイギリスとは物価が違います。基本的に日本の中では通常、「グミ」というカテゴリーでいったら、100円から、高くてもは500円などそのぐらいの間で、買えるものがCBDが入った瞬間に、2000円とか3000円になってきます。ものによっては5000円までしてきます。となってくると、やはりどうしても「グミ」というカテゴリで考えると、高く思われますので、「手を出しづらいな」と思います。
皆さんもご存じかもしれなませんけど、CBDというのは体感がとても食べた瞬間その日からわかるみたいなものではかったりします。なので、「せっかく高いお金を出したのに、何もわからない」、「しかも大麻由来と聞いてちょっと期待したのに全然違う」という声も上がります。
実はCBDはそれぞれ人に適した量があって、それを続けて頂くことが大事なんですけど、そこにたどり着かないでやめてしまうのが多くて、それでCBDをむしろがっかりした人も一定数いらっしゃいますので、価格が下がって継続的に摂取しやすくなるというところがやはり重要になります。
今上げた3つの要素は、CBDに対する認知度そのものの拡大と、理解度をもう少し広めることと、最後に価格を下がるということ。この3つがあれば、かなりCBDについては市場がもう少し伸びる、エンジンになるのではないかなと思っております。ただそこはやはり、規制緩和が関わってくるので、どうしてもそこと切り離せないのですけど、少し違う文脈ではそういったことになるのかなと考えております。
増野:ありがとうございます。先ほど日本での検査が話題に上がりましたね。日本大麻取締法は部位でやっているので、特有の検査と証明書があります。
すでに色々弊社に来る問合せの中で、北米、ヨーロッパである程度商売をしている企業さんがあります。そのような企業が日本市場に進出しようとする際に、特殊なルールのもとに検査が行われると思うのですけども、特に海外企業が注意する点がありましたら是非お知らせください。
YASUTA ARASHIRO: はい。そうですね。日本では輸入の際に成分分析書というものを出さないといけないことにされておりますので、海外から見ると、日本に輸出する際に、そのCBDの原料の中に、THCが含まれていないことを確認するためにこの成分分析書というものを提出必須としております。それで、この成分分析書というのが海外企業の方にとって特に気にした方が良いかと思うところではあります。
続きまして、特に実は日本の輸入の決まりでは、どういった検査機関で検査をしないといけないという規制は実はなかったりします。なので、検査機関によってはクオリティーに差がどうしてもあるのですけど、そこについては日本では問わないこととされております。正直そこはどうでしょうかというところはありはすしますけど、分析機関については基本的に基準があるわけではないという特に気を付けて頂きたいことが1つあります。
ただ、もう1つ気を付けないといけないところで、成分分析書に定量限界、いわゆる「LOQ」(Limit Of Quantitation)というような検出をすれば、定量できる限界値というものと、あとはLimit Of Detection(LOD)(検出限界値)というものがあります。成分分析書によっては、定量限界(LOQ)しか書いていない成分分析書があります。しかしそれについては、日本は認めない扱いになっているので、気を付けて欲しいですね。
日本としてはTHCが入っていないことの証明として、あくまで検出限界値(Limit Of Detection)の記載が必要となりまして、Limit Of Detectionがいくらで、それで基本的には検出されて「THCが検出されていません」というのは記載が必要とされていますので、海外の方が日本に輸出する際には、そこだけ注意していただきたいですかね。
あとは、輸出した後に、とある商品に「THCが入っている可能性がある」のような内部通報などを受けて、厚生労働省が調査することがあったりもします。あとは、CBD商品だと思って持ってたものが、日本の警察が「大麻が入っている」という疑いをかけて、調査することがあります。
それについては、どんなにその輸入の時点で、「ちゃんとTHCが入っていませんよ」といっても、そこで検出されてしまったら、基本的には「THCが検出されました」ということで、逮捕されてしまったりですとか、厚生労働省に、このメーカーのこの商品のこのロットに、THCが入っていたので気を付けてください、回収してくださいみたいな話が出てきます。そういった面では、極力THCはゼロに近づける努力をする必要があるとは思っております。
増野:承知しました。弊社に来る問い合わせで、いくつかあるのが、「サンプルをとりあえず送りたい」、要するに日本の事業者、ディストリビューターなどを見つけて、日本にも売りたいという企業さんがいくつかあります。「サンプルを送って、試してもらえばわかる」という自信満々の企業からの問い合わせですね。
そういった際にも、手順としては全く同じでしょうか?日本ではまず、輸入者を特定して、その方が日本での検査したものを、THCが入っていないし、茎の部分しか使われていないなどの証明という手続きをしたうえで初めて、サンプルを受け取ることができるという理解で間違いないでしょうか?
YASUTA ARASHIRO: はい、その理解でございます。なので、少量を送る場合でもそのプロセスが求められるので、かなり重たいものになっております。

Ken Masuno: 承知しました、ありがとうございます。また規制緩和の話に少し戻りますけども、現状想定されている規制緩和が来ると、部類への証明、つまり「茎しか使っていません」というような証明はいらなくなるということは、企業からすると1つやることが減ると思いますね。この規制緩和による検査に限った場合に何か、それ以外に影響はあるとお考えでしょうか?
YASUTA ARASHIRO: そうですね。基本的には成分規制が導入されるにあたって、厚生労働省の方で、例えば残留THCといいますか、どうしても0.00PPMにするのはかなりコストがかかって難しい状態があります。それで、アルコールみたいな感じで一緒に、アルコール0%といっても厳密には少し入っているみたいなパターンもありますので、それと同じような形で、「人体に影響はない範囲で、下限値というの求めていいではないか」という動きにはなっております。
基本的には、これはまた確定ではないのですけど、製品検査に関してはその検出限界値が定められたら、それを絶対下回る形の検査をする必要があると思っております。製品検査につきましては、今後日本でかなり需要は増えてくると思います。
なぜなら、成分規制によって成分自体に着目されるので、そこはかなり重要ではあるのですけど、正直日本ではまだ、ちゃんと検査できるような検査機関、あとは「どういった基準で検査をしないといけない」というのを示すガイドラインが整備されていない現状でございます。
なので、そういった形が今後整備する意向があると厚生労働省の担当者はインタビューで答えはしていますですけど、基本的にはまだ未確定な部分ではあります。そういった成分検査については、影響としてはそもそもそこを担える企業が国内にないという問題点もあります。あとは、検査を海外でやり、代替しようとなった場合に、どのような基準を設けるべきか、海外についても色々国際的な企画手順とかもございますので、それを求めるべきのか、みたいな話もあります。
なので、そういったところが製品検査の影響に規制緩和であるところだと思います。コストにつきましては、やはり求めるものが高くなれば高くなるほどどうしてもその製品検査ができる所、受け入れ先が少なくなってきます。そしたらどうしてもコストとしては競争力があるので、高くなる傾向にもあることは想定されると思います。
ただ、検査内容自体は正直あまり変わらないので、そこについてはあまり大きな影響はないのかなと考えております。なので、一番規制緩和において重要なのはやはりその「どういったレベルの検査を求めるのか」を国がちゃんと示してくれるかどうかですね。これについてはまた未定なので、そこが一番重要になってくるかと思っております。
Ken Masuno: ありがとうございます。弊社の方で用意した質問は以上ですので、今日は貴重なお時間を本当にありがとうございます。
YASUTA ARASHIRO: ありがとうございます。
Ken Masuno: 最後にですね、先生が日本でCBD弁護士としてご活躍される中で、情報収集などに使うウェブサイト、SNSのアカウントなどにもし、差し支えがない範囲で教えていただければと思います。
YASUTA ARASHIRO: そうですね。情報収集というと、私が弁護士でありますので、どうしても一次情報に当たらないといけないというところがあります。なのでわたくしは面白くない回答かもしれませんけど、情報収集は基本的に厚生労働省で行われている有識者の会議ですとか、検討会、そういったところは一番主にしております。
あとは、なかなかSNSに出てこないような、国会議員の団体さんのところで提出されている資料、そういった国会議員の方が出席されている勉強会での資料などもあります。そういった所に行って、直接人と話して情報を取るようにしております。
SNSにつきましては、正直今の現状において、あまり情報収集という観点で有益なアカウントはあまりないのかなと思いますね。私がたまに発信しているので私のツイッターをフォローしてくれると嬉しいです。
あとはそうですね、アメリカの方で結局その大麻に関しては合法な取り扱いで、色々なビジネスが始まっています。私は個人的にアメリカで、大麻を扱うロイヤーが何をしているのかというのはかなり見たり、追っかけたりはしております。アメリカのノースカロライナ州で有名のロッド・カイト弁護士という方がいらっしておりまして、その人のウェブサイトを私の方で追っかけて見てはおります。
Ken Masuno: ありがとうございます。
新城安太弁護士は東京にある至誠法律事務所のCBD・ヘンプ/通販・広告/医療機関・医療ビジネス(主に自費診療)に特化している弁護士です。約3年前にCBDに関わりだしてから、日本におけるCBD法律の第一人者となり、業界の最新動向を常に把握しています。新城先生のウエブサイトはこちらから、ツイッターはこちらからフォローできます。
東京エスクはロンドン、アムステルダムを拠点とする市場調査会社です。私たちの使命は、ヨーロッパ市場をネイティブに理解する弊社だからこそ描ける興味深い文化的洞察を提供することにあります。お客様のヨーロッパ市場進出を市場調査、現地パートナービジネスマッチング、ローカライゼーションという3つの観点からサポートします。30分の無料相談をご希望の場合はこちらからご連絡ください。
Tokyoesque とソーシャルメディアで繋がりませんか?以下のページからフォローをお願いします。




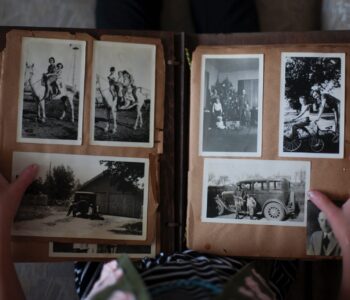



![[2022年版]イギリスでこれから伸びる3つの業界 UK](https://tokyoesque.com/wp-content/uploads/2022/01/charles-postiaux-Q6UehpkBSnQ-unsplash-scaled.jpg)