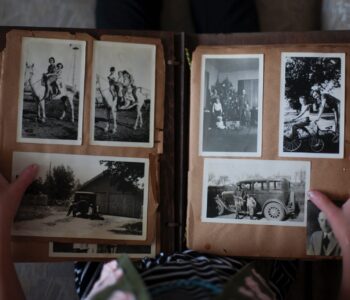ヨーロッパで広がる日本食市場(2025年)

なぜ今ヨーロッパへの輸出が重要なのか
日本食市場では、ヨーロッパでの浸透度が高まっています。健康志向の広がりや、日本文化への興味が後押しとなり、寿司やラーメン、抹茶スイーツなどが珍しくない存在になっています。今では多くの都市で、日本食は日常的に楽しめる定番の料理となっています。IMARCのレポートによると、ヨーロッパのエスニック食品市場は2024年に約175億米ドルの規模を記録し、2025年から2033年にかけて年平均成長率7.10%で成長し、2033年には約336億ドルに達すると予測されています。こうした成長する需要は、日本の食品・飲料企業にとって、海外市場への展開にぴったりのタイミングとなっています。
本物らしさ
ヨーロッパでは、本物の日本食が求められるようになっています。特にオランダでは、日本の食材や日本人のシェフが作る料理を提供するお店が人気です。例えば、アムステルダムの「Yamazato」や「Sazanka」などのレストランでは、新鮮な寿司や日本の伝統的な料理が楽しめます。これらのお店は、地元の人々にも愛されており、日本の味を大切にしています。こうした傾向は、日本食市場の広がりを示す好例といえるでしょう。
日本のシェフは、特定の料理ジャンルに特化していることが多いです。例えば、お寿司屋さんではラーメンが出てくることはほぼなく、逆もまた然りです。居酒屋の厨房は柔軟性がありますが、焼鳥専門店の焼鳥には敵いません。このような専門性は日本では一般的で、オランダ市場でもシェフが特定のコンセプトを持ち込むことで反映されています。日本食市場における競争力を高めるためには、「すべての日本料理」を提供するのではなく、うどん専門店やてんぷら屋さんなど、特化したコンセプトを導入する余地があるということです。これは、投資家にとっても大きなビジネスチャンスとなります。

立地の重要性
ドイツでは、最新の政府報告によると、約100軒のレストランのみが「本物の日本食」として認められています。これは、真の日本食がいかに希少で、日本食市場において際立っているかを示しています。このような状況はドイツに限らず、イギリスやヨーロッパの地方都市でも見られます。日本食の需要は明らかに高まっているものの、多くの地域では本物の日本食にアクセスできないのが現状です。これは、日本の企業にとって、こうした未開拓の地域に焦点を当てて輸出や展開を行う絶好の機会となるでしょう。
シェフィールド(イギリス)、リーズ(イギリス)、リヨン(フランス)、ヨーテボリ(スウェーデン)などの都市では、活気ある食文化と、世界の料理に興味を持つ若い消費者が増えています。こうした都市は、今後の日本食市場拡大において重要なターゲットとなり得ます。日本から進出している企業の一例が、丸亀製麺(Marugame Udon)です。2023年初め、ロンドン以外では初めて、イギリスのレディングに店舗をオープンしました。その後、ブロンリー、ケンジントン、ウォータールー駅、カナリー・ワーフなどにも展開しています。
丸亀製麺の特徴は、オープンキッチンの「うどん工房」スタイルです。シェフが目の前でうどんを作る様子を楽しめます。デザインを担当したのは、ブランディング会社のハリソンです。最初は、イギリスの客が「自分でトレイを片付けるとは思わなかった」と言っていましたが、実際にはその習慣がなかったため、トレイを片付ける専用のエリアを設けました。地元の習慣を取り入れることで、他の競合店との差別化を図っています。

Tokyoesqueは、日本料理がヨーロッパで成功するためのサポートをしています。
現地の文化や味の好みをしっかり理解し、ブランドの魅力を効果的に伝える方法をご提案いたします。どうぞお気軽にご相談くださいませ!
何かご質問などございましたら、お気軽にこちらよりお問い合わせください。